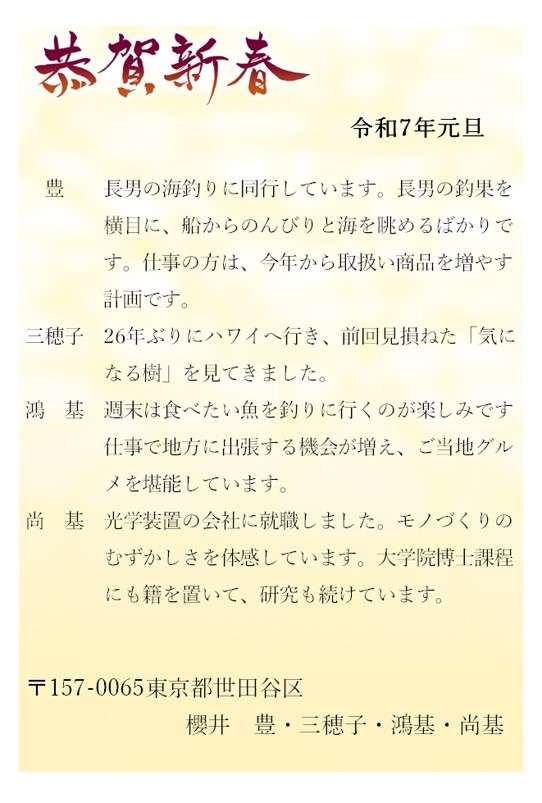Rioさんのインタビュー技術が光る内容だったと思います。素晴らしかったです。
国際的な活動への取り組みや若者育成に向けた取り組みなどは、個人的には実際に手足を動かすところのスピード感には不満が残るものの、方向性については賛同できるものでした。
一方で、まずいなぁ、と思ったのは、日本版電子QSL的なものを開発しようとしている、という話でした。世界動向を無視したガラパゴスシステムはやめた方がよいと思うからです。
hQSLについては、Emailをベースにするのは危険だと心配になります。ネットワークセキュリティ分野に携わった経験から、そう思います。(以前には、日本ネットワークセキュリティ協会JNSAで役員を務めていたこともあります。)
また、Rioさんが鋭く突っ込んだ、総務省のみならず各業界に対する人脈を具体的にどうやって広げてゆこうとしているのか、という質問に対しては、明らかにノーアイディアの様子が垣間見えて少し残念でした。既に人脈を持つ人をうまく利活用してゆく姿勢が望まれます。(この「既存の人材を利活用する」というのが、これまでJARLが一番苦手としてきたことのようにも思いますが、やる気になれば難しいことではないと思われます。)
前向きな議論を重ねることも大事ですが、Rioさんが指摘しているように、少々間違った方向になってもよいから実際に手足を動かし、軌道修正しながら進めてゆくという「実行力」が、もう少し見えてくるとよいですね。現代は「見える化」がとても重要ですから。
一方、会員などの総意を充分にくみ取って改革するという考え方は、現代ではうまく行かない手法とされていますので要注意です。
「アフォーマティブ・ビジネス vs クリティカル・ビジネス」という考え方がビジネスの世界でも注目されているように、これからのマーケティングは「総意」をくみ取っても駄目だと言われ始めています。次のURLなどが参考になるかと存じます。
https://ambitions-web.com/articles/critical
島根QSLビューロについては、毎月でしょうか(?)、非会員、あるいはQSL転送費用を支払っていない終身会員宛に65,000枚のカードが届いているというお話に驚かされました。
ということは、それなりにオンエア・アクテビティの高いハムが、ビューロ経由のカードは必要ないからと会員になっていない、あるいは終身会員であってもQSL転送費用を支払っていない、という風に理解できることに気づかされます。
JARLは、この視点に気づいているのか、少し心配です。
気付いていないとしたら、非会員あるいはQSL転送サービスを受けていない終身会員宛にカードをビューロに送らないようにしてもらうにはどうしたらよいだろうか、というおそらく解決不可能な命題にのみ頭を悩ませているのではないでしょうか。このアプローチは「労多くして功少なし」かもしれません。
発想を変える必要がありそうに思います。
上で述べたような新しい視点で何か策を講じようというのであれば、大変かもしれませんが、非会員宛とQSL転送費用を支払っていない終身会員宛と、それぞれがどの程度の割合を占めているかの調査が必要かもしれません。
全数調査でなくとも、どこかの時点での抜き取り調査でよいと思いますので、大変かもしれませんが手を動かし、汗を流す価値はあると思います。
そのうえで、そもそもビューロを必要としないからと会員になっていない、しかしオンエアすることにアクティブなハムには、QSL転送以外の何を訴求すれば会員になってくれるのかの調査が、そのQSLカードの宛先をベースに聞き取り調査が可能かもしれません。ターゲット情報があるのですから、非会員宛カードは宝の山です。
QSL転送費用を支払っていない終身会員については、枚数によっては、実は終身会員のQSL転送を再び無料化した方が、トータルコストはかからない、ということにもなりかねません。
とにかく、的を射たファクト調査を実施し、それをベースに策を講じるようにしなければ、何をやっても的外れになりはしまいかと心配になります。